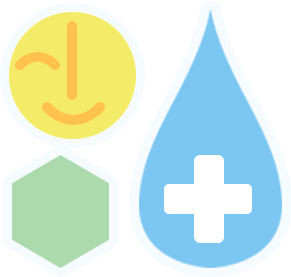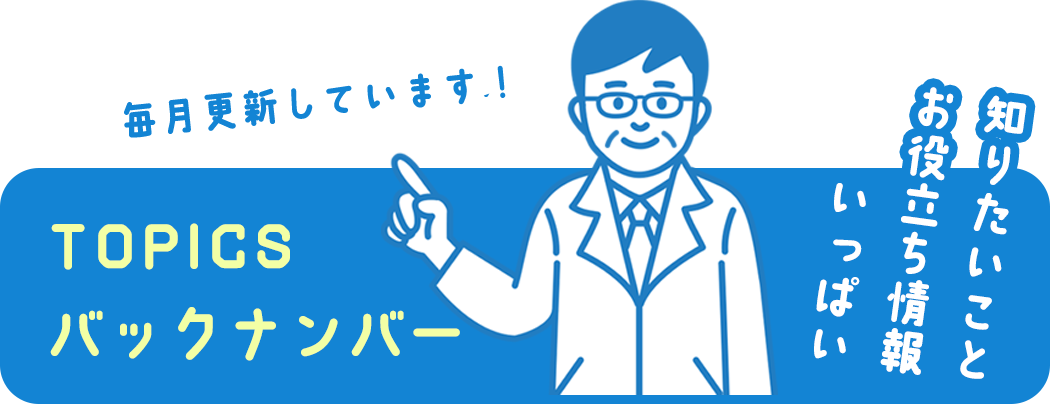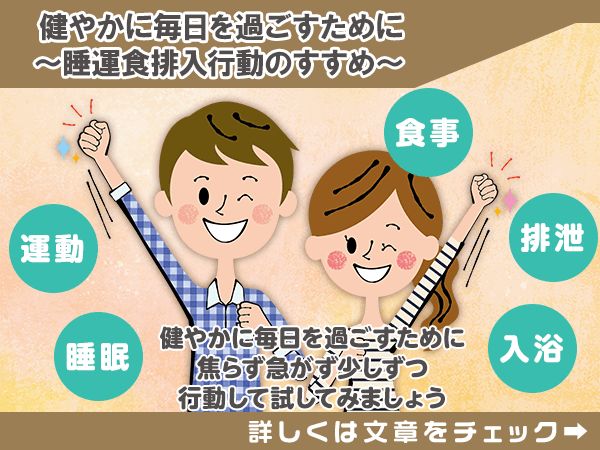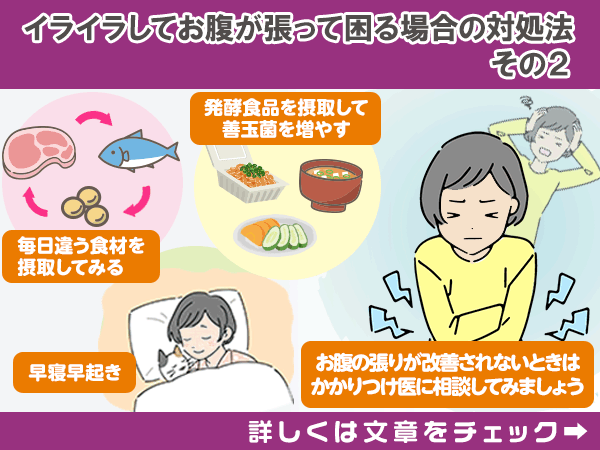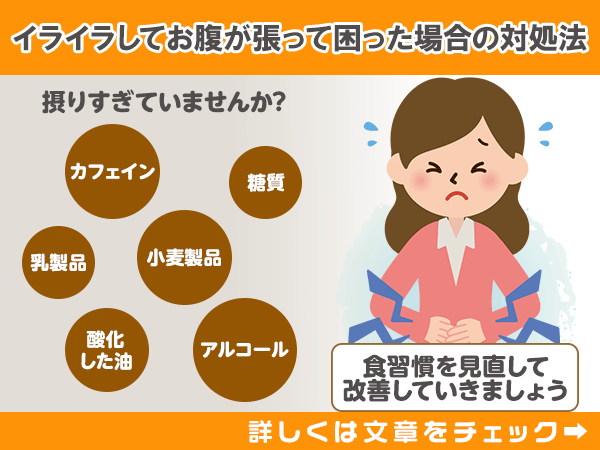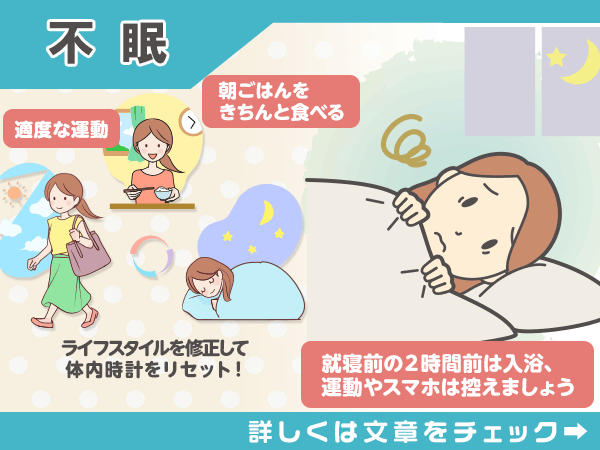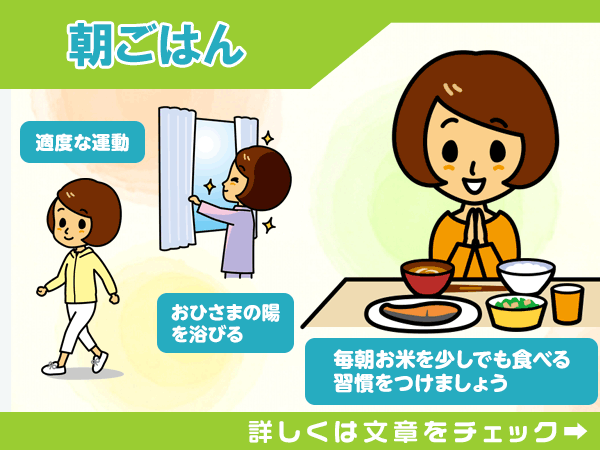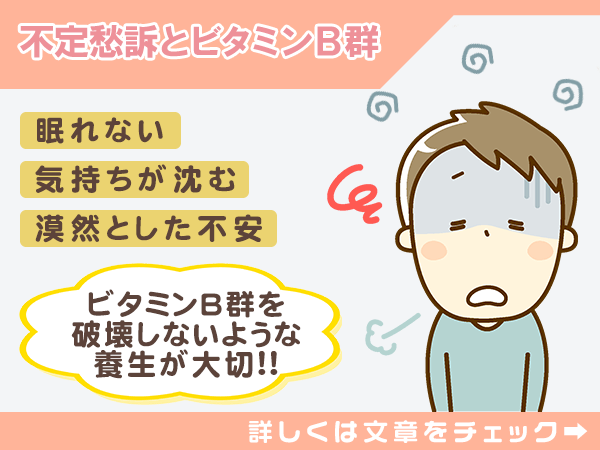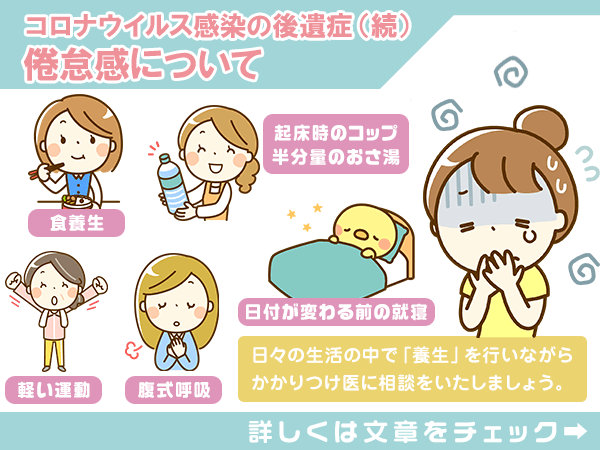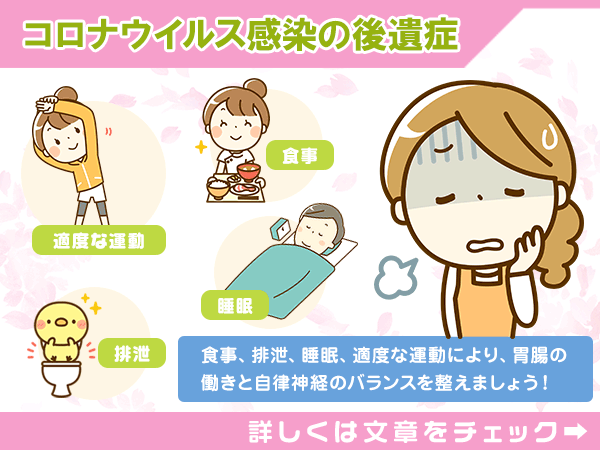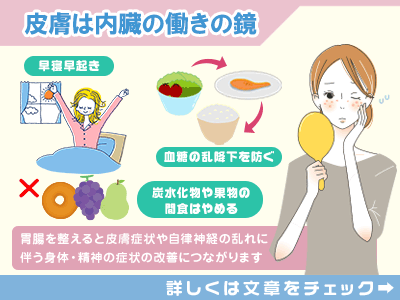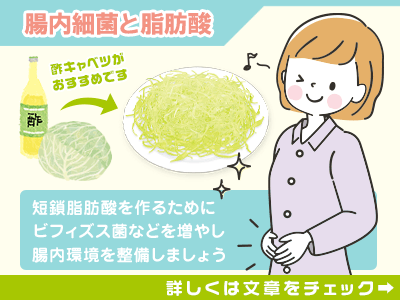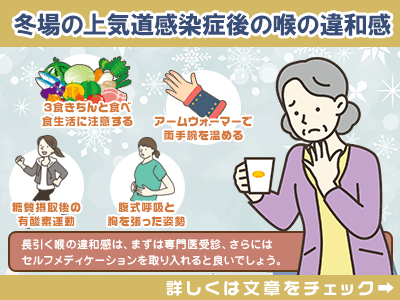ここ北部九州においても、寒さが肌身に感じられる季節になってきました。毎年、季節の変わり目、具体的には寒暖差が大きくなる時期ですが、この季節は自律神経の乱れが生じやすく様々な身体症状、精神症状が出やすくなります。頭痛、肩こり、めまい、蕁麻疹、不眠、イライラ、寒暖差による鼻炎など年齢性別に関係なく自律神経の乱れに伴う諸症状が生じやすくなってきます。
これら自律神経の乱れを来しやすい方にはある傾向があるようです。具体的にその誘因と対策について述べてみたいと思います。
1.睡眠の質が悪い方(入眠障害、熟眠障害):できれば日付が変わる前までに寝ることと入眠前はスマホなどのブルーライトを見ないこと。質の良い睡眠は自律神経の乱れを改善してくれます。
2.胃腸に負担が多い食事(アルコール、甘いもの、辛い物、脂っこいもの、冷たい物)を過度に摂取している方:胃腸の粘膜に負担をかけてしまい、十分に消化吸収が出来ず必要な栄養素が足りなくなって自律神経の乱れを来すので、これらの食材は控えること。さらに、毎日排便する習慣をつけること
3.座って仕事をする時間が多く、適度な運動が足りない方(血液循環が停滞しやすくなるため):休み時間や食事後にラジオ体操や早歩きを数分でも行うと良いでしょう。
4.薄着傾向の人や手首、足首が冷える方(血液循環不全に陥りやすいため):5本趾の靴下、ルーズソックス、アームウォーマー、スカーフあるいはハイネックを着用して冷え対策を行うと自律神経のバランスが整いやすいです。
これらの対策を行うと寒暖差に伴う自律神経の乱れによる様々な症状の予防につながると思います。それでもだめならば、かかりつけの先生にご相談なさると良いでしょう。皆様方お一人お一人、セルフメディケーションにつとめられることをお薦めします。